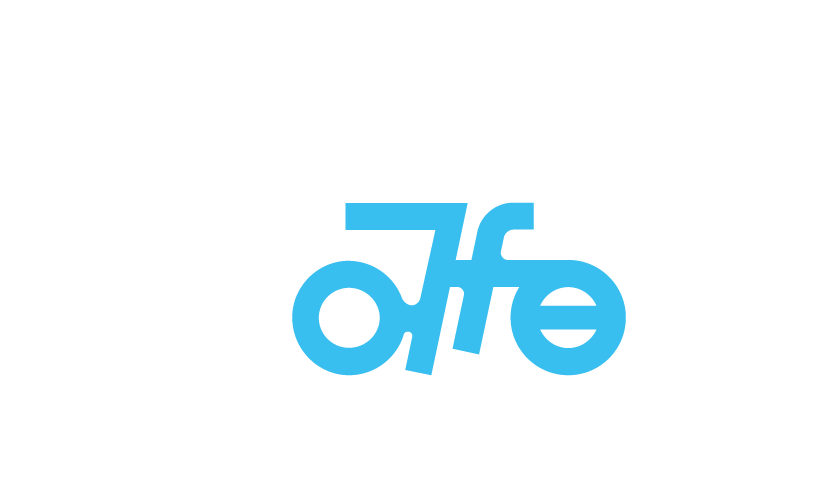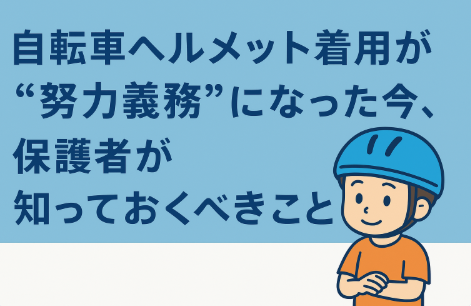こんにちは、Cycle Safety Projectです。
2023年4月から、自転車のヘルメット着用が全年齢で「努力義務」となったこと、ご存知ですか?
とはいえ、「努力義務って結局、かぶらなくてもいいんでしょ?」と思っている方も少なくないかもしれません。
でも実は、この“努力”の背景には、深い意味と切実な事情があるんです。
今回は、特に子どもを育てる保護者の皆さんに向けて、
なぜ家庭での声かけが大切なのか
努力義務化のポイントヘルメットが命を守る確率
なぜ家庭での声かけが大切なのか
などを、わかりやすくお伝えしていきます。
子供の未来の為に安全を選びましょう
目次
まず、2023年4月に改正された道路交通法により、すべての自転車利用者に対し、ヘルメット着用が努力義務化されました。
もともと「13歳未満の子どもに着用させること」は2008年から保護者に義務づけられていましたが、それが今回、
- 大人も含めた「すべての利用者」に拡大された
- 運転者本人にも「努力義務」が課された
という点で、大きな転換点となりました。
「努力義務」とは法的強制力がない代わりに、「やるべきこととして社会的に求められる行動」です。
つまり、「罰則はないけれど、万一の際に“なぜ着けてなかったのか”と問われる可能性がある」ということ。
とりわけ、子どもが事故に遭った際には、保護者の姿勢や家庭での教育の有無が見られるケースも増えています。
警察庁の発表によれば、自転車事故による死亡者の6割以上が頭部に致命傷を負っているというデータがあります。
また、ヘルメットを着用していれば、死亡率は約4分の1に減少するという調査も。
これは、極端に言えば──
「かぶっていれば助かったかもしれない」
「かぶっていたおかげで命が助かった」
そんな境目にある、たった1枚の“帽子”なんです。
では、なぜ多くの子どもたちがヘルメットをかぶらないのでしょうか?
Cycle Safety Projectが行った独自ヒアリングでは、こんな声が聞かれました:
- 「恥ずかしいから」
- 「暑いしムレる」
- 「友達がかぶってないから」
- 「親もかぶってないし」
……思わずドキッとしませんか?
子どもはとても敏感です。
「誰がかぶってるのか」「親がどうしているか」を見て、自分の行動を決めるんです。
つまり、ヘルメット着用は「家庭文化」に近いもの。
親がかぶれば子もかぶる、逆に親がかぶらないと、子も“かぶる理由”を失ってしまうのです。
では、どうすれば子どもに自然とヘルメットをかぶらせられるのでしょうか?
私たちは、次の3つのアクションをおすすめしています。
① 親も一緒にかぶる
大人がかぶれば、子どもは「かっこ悪い」と思いません。
むしろ、「うちの家族って安全意識が高いんだ」と、自信にもなります。
② 選ばせる:デザインは“子ども主導”で
「これがいい!」と自分で選んだヘルメットは、子どもにとって“お気に入りのアイテム”になります。
自転車とおそろいカラーにしたり、キャラクターものを選んだり──そういう工夫も、意外と効果ありです。
③ 家族で「安全ってかっこいい」を共有する
ヘルメットをかぶる=まじめ、ダサい──そんなイメージは、もう古い。
「安全のために選択できること」が、今の時代の“かっこよさ”です。
事故例を家族で話題にすることも、大事な教育の一つになります。
実際に、日本各地で「ヘルメット未着用による重大事故」はあとを絶ちません。
ある関東地方の小学校では、通学中の児童が車と接触し、転倒。
頭を強く打ち、1週間意識が戻らない状態が続いた――という事例がありました。
学校側は「交通ルールを守っていた」と証言しているものの、ヘルメットは未着用だったそうです。
保護者は後日、「朝に急いでいたから、“今日はいいか”と声をかけなかった」と話していたといいます。
事故は不意に訪れます。たった一言の声かけや、数秒の行動が、命を守る分かれ道になることもあるのです。
子どもが今日かぶるかどうか、明日も続けられるかどうか。
それを支えるのは、親の「声」と「習慣」です。
- 毎朝「今日もかぶった?」と声をかける
- 一緒にヘルメットを選ぶ・かぶる
- 雨の日や暑い日でも、例外をつくらない
小さな積み重ねが、子どもの「命の習慣」になっていきます。
どうか、“その日”が来る前に──家族みんなで、ヘルメットの意味を見直してみてください。
子どもが転んだとき、坂道でバランスを崩したとき、交差点でヒヤッとしたとき。
そのすべての瞬間に、たった1つのヘルメットが命を守ってくれるかもしれません。
そしてその習慣は、あなたの声かけ一つで始まるものです。
法律が変わった今こそ、家族でヘルメットについて考えてみませんか?
「かぶっててよかった」より、「かぶってて当たり前」な社会へ。
Cycle Safety Projectは、その一歩を応援しています。