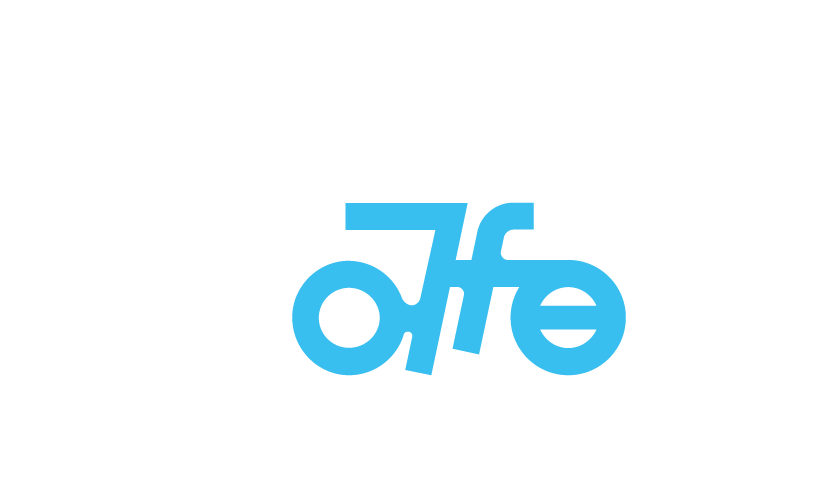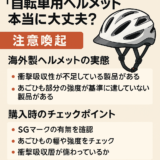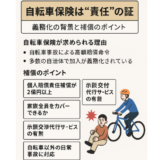2023年4月、自転車利用者へのヘルメット着用が“努力義務”となってから、まもなく2年が経とうとしています。警察庁の発表によると、全国の着用率はおおよそ17%。決して高いとは言えない数値ですが、都道府県ごとのデータを見ると、より大きな問題が浮かび上がってきます。
その最たる例が私たちの暮らす大阪です。大阪府内におけるヘルメットの着用率は、わずか「5.5%」。全国平均を大きく下回る結果です。
今回は、なぜ大阪ではヘルメット着用が進まないのか、そして命を守るために私たちが今からできることについて考察を深めてみたいと思います。
大阪で自転車用ヘルメットの着用率が上がらないのは何故?
目次
まず初めに、大阪における自転車の位置づけについて整理しておきましょう。
大阪府、特に大阪市内では、自転車は「生活の足」として非常に密接な存在です。通勤・通学・買い物・子どもの送迎まで、自動車や公共交通と同等かそれ以上に活用されています。坂が少なく、駐輪場所も比較的多いため、「手軽で便利な移動手段」として日常生活に根づいています。
しかし、この“手軽さ”がヘルメット着用率の低さと表裏一体になっていることも見えてきました。
「ちょっとそこまで乗るだけだから…」
「暑いし、見た目も気になるから…」
「努力義務なら無理して被らなくてもいい」
こうした声は、ニュースの中でインタビューに答えた市民の皆さんからも聞かれました。これはまさに、「安全」と「利便性・快適性・見た目」とのバランスの中で、多くの人が“着用しない”という選択をしてしまっている現実を表しています。
制度として「努力義務化」が導入されたことで、法的な拘束力はありません。つまり、被らなくても罰則はない。これが逆に、「被っても被らなくてもいい」と受け取られやすい土壌を作ってしまっています。
また、制度開始から2年が経過しているにも関わらず、「そもそも努力義務になっていたことを知らなかった」という声も未だ多いことには驚かされます。これは、国や自治体による広報のあり方にも課題があると感じます。
私も行政書士として日々さまざまな法改正や制度変更に触れていますが、「制度を作ること」よりも「正しく届けること」「意識を変えること」の方が何倍も難しいということを痛感しています。。
私がみたニュースの中では事故によって実際に重傷を負った方の声や、着用の重要性を訴える自治体の取り組みも紹介されていました。
特に印象的だったのは、ある女性の「事故で自転車が飛び、頭を打って意識を失った。幸い命は助かったが、今は必ずヘルメットを被るようになった」という言葉でした。事故は“誰にでも起こりうる”ものです。経験者であるからこそ、その重みが違います。
ヘルメットを被ることで、致命的な頭部損傷のリスクが70%以上減少するというデータもあります。これだけは数字の上だけではなく、現場の救急医療や遺族の声からも実証されている事実です。
着用率が低迷している中でも、私たちにはできることがあります。行政書士として、また一生活者として、以下の3つを提案したいと思います。
① デザイン性の高いヘルメットの選択肢を広げる
「ダサい」「重い」「暑い」といったイメージが、着用のハードルを高くしています。最近では、カジュアルで帽子のように見えるヘルメットや、折りたためる軽量モデルなども増えてきています。特に若者や女性、高齢者にも受け入れられるようなラインナップを行政や企業が共同でPRすべきです。
② 学校や地域での啓発活動
制度として義務化されていなくても、地域で“常識”にしていく力はあります。小中学校やPTA、町内会でのヘルメット講習、着用モデル事例の紹介など、地道な啓発活動が意識を変えていく鍵です。
③ 安全と利便性のバランスを取る仕組み作り
たとえば、自転車保険加入の条件として「ヘルメット着用を推奨する」ことや、「着用者に保険料割引を提供する」といったインセンティブの導入も有効です。民間と行政が連携すれば、より現実的な解決に結びつきます。
自転車のヘルメット着用は、法律の問題である前に「命をどう守るか」という自分自身の選択の問題です。
「義務じゃないからいいや」と考えるのではなく、「自分や大切な人の命を守るために、できることからやってみよう」と行動を起こす人が一人でも増えていけば、大阪の数字も必ず変わっていくはずです。
制度は万能ではありません。だからこそ、制度に頼るだけでなく、“私たち自身が変わること”が何より大切だと感じます。
私も、このような情報を今後も発信していくことで、一人でも多くの方が「ヘルメット、被ってみようかな」と思っていただけるよう、微力ながらお手伝いできればと思っています。