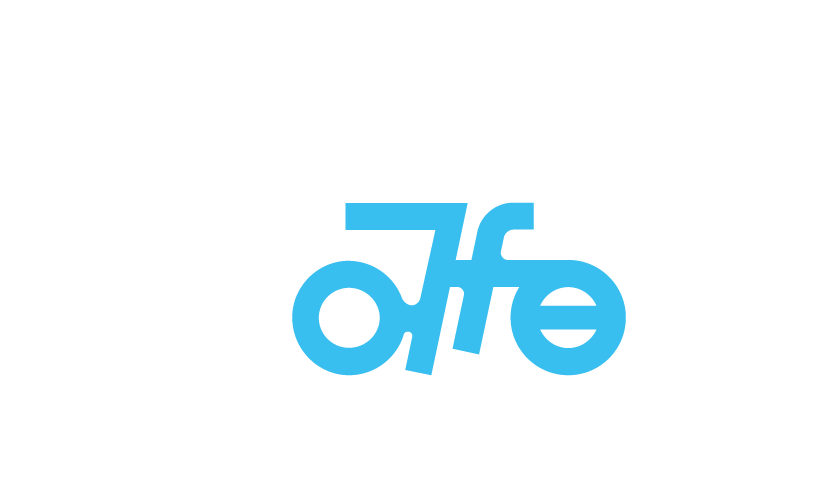ここ最近、街なかで増えていると感じるのが、自転車利用者による接触事故や危険な運転。特に都市部では、自転車は生活に密接に根づいた移動手段であり、もはや“日常の一部”といっても過言ではありません。
だからこそ今回は、事故を未然に防ぐための「本当の意味での安全」について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
事故を未然に防ぐには普段の心構えが大事ですよね
目次
世の中には「これさえあれば安心」「万が一に備えて」といった商品や情報が溢れています。確かに、そういった備えはあるに越したことはありません。しかし、それよりももっと基本的で、効果が高いのは「普段の行動そのものを見直すこと」だと私は考えています。
どれだけ頑丈な装備があっても、信号を無視して交差点に進入すれば事故は起きますし、逆走やスマートフォンを操作しながら走っていれば、いずれ大きなリスクに直面することになります。
つまり、「安全」というのは、特別な何かを加えることではなく、日常の選択を正しく積み重ねていくことなのです。
最近では、車両との接触だけでなく、自転車同士や歩行者との衝突といった事故も増えています。特に都市部では人通りも多く、道路の構造上、自転車がどこを通れば良いのか分かりにくい場面も少なくありません。
交差点や見通しの悪い曲がり角では、歩行者に気づかずに接触することもありますし、坂道でブレーキが遅れてしまえば、思わぬ転倒事故にもつながります。これらの事故の多くは、「あと少し注意していれば」「もう一呼吸おいて確認していれば」防げるものです。
では、どうすればこうした事故を防げるのでしょうか?
答えは「特別なことをしようとしない」ことだと私は思います。以下、私自身が日頃から意識している基本的なポイントを挙げてみます。
一時停止を“形式”ではなく“本気”で行う
「止まったつもり」「徐行だから大丈夫」と思いがちですが、それでは事故は防げません。交差点に入る前に、しっかりと止まって、左右だけでなく斜め後ろまで確認する習慣をつけましょう。
道路は“共有空間”であるという意識を持つ
歩行者、自動車、バイク、それぞれが互いに空間を共有しているという感覚を忘れないことが大切です。自分のペースで進みたくても、他者の存在を無視すれば、それは一瞬で“危険”に変わります。
「ながら運転」は“注意散漫運転”と心得る
音楽を聴きながら、スマホを見ながら、考え事をしながら――。これらはすべて「ながら運転」にあたります。自転車は意外にもスピードが出る乗り物です。少しの気の緩みが、大きな衝突や転倒に直結します。
夜間・早朝は“見られること”を意識する
車や歩行者から自分がどのように見えているかを意識しましょう。街灯が少ない道、住宅街の十字路などでは、相手に自分の存在を認識してもらうことが何よりの安全策です。
自転車は歩行よりも自由で、スピードも出せて便利ですが、法律上は「軽車両」として扱われています。つまり、自動車と同様に、道路交通法に則って運転しなければならない義務があるのです。
無意識のうちにルールを破っているケースは少なくありません。「歩道を猛スピードで走る」「車道を逆走する」「一時停止を無視する」――これらはすべて道路交通法違反であり、万一事故になった際には重大な過失責任を問われる可能性があります。
特に意識しておきたいのが、自転車に乗っているときは「被害者」になるだけでなく「加害者」にもなりうるということです。
過去には、小学生の自転車が歩行者と接触し、1億円近い賠償命令が出されたケースもあります。もちろん、親が責任を負いました。日常の延長線上に、これほどのリスクが存在しているという事実を、私たちはもっと重く受け止めなければなりません。
自転車は、現代社会において非常に合理的で、誰にでも身近な乗り物です。だからこそ、「当たり前にあるもの」の怖さを忘れてはいけません。
制度や法整備、技術の進歩も大切ですが、一番の安全対策は「私たち一人ひとりの意識」にあります。
特別な準備や大きな投資がなくても、
“止まる” “見る” “譲る” “考える”――
この4つの行動を心がけるだけで、自転車事故は確実に減らせると、私は信じています。